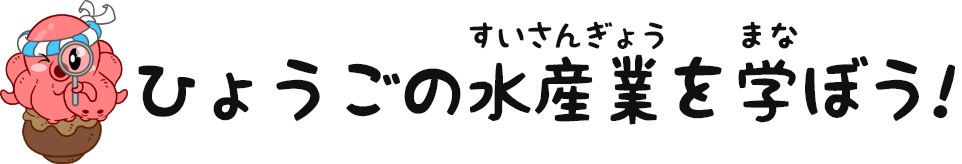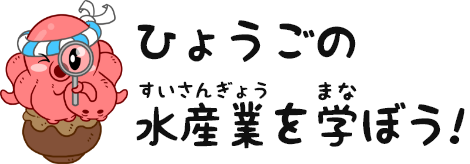古くから明石で獲られてきた水産物からランダムに10問出題します。
漢字の読み方をカタカナで回答してください。
白魚
解説

体長6~10cmほどの細く体幅の薄い半透明な魚です。千種川加工では、2~3月の短期間のみ産卵に来遊してくる親魚を狙った刺網漁が日暮れと共に行われ、春の風物詩となっています。
主に天ぷらや玉子とじ、吸い物にされます。
(写真提供:姫路市)
鰡
解説

大きいものでは80cm近くなり、河口周辺や沿岸域に群れで生息しています。
冬場のボラは”寒ボラ”と呼ばれ、あっさりとしながらも旨みのある美味しい魚ですが、最近では、生息場所によっては肉に臭みがあることから、市場に出ることはあまりありません。
ボラの卵巣を塩漬けにした「カラスミ」は日本三大珍味の一つです。
(写真提供:姫路市)
章魚
解説

主にマダコを言い、他にイイダコ、テナガダコなどがあります。
マダコは6~9月が主な産卵期となり、8~7月の「梅雨ダコ」が旬とされていますが、11月からの低水温期の方も旨味が増しているとも言われます。
(写真提供:姫路市)
蟹
解説

ズワイガニやガザミ等がいます。
ガザミはワタリガニとも呼ばれ、後ろの脚が平らなオール状になっており、泳ぐこともできます。播磨灘全域に生息しており、一年を通して底びき網漁やたて網漁で漁獲されます。
(写真はガザミ/写真提供:姫路市)
赤貝
解説

殻長10cmほどになり、ふくらみが大きく、殻表面は黒褐色の短毛に覆われた放射肋(ろく)が40数本あります。
播磨灘北部では、低水温期に底びき網漁で漁獲されます。
(写真提供:姫路市)
魬
解説
有名な出世魚で、関西ではモジャコ(~10cm)→ツバス(30~40cm)→ハマチ(40~50cm)→メジロ(50cm~80cm)→ブリ(80cm~)と呼び名が変わります。
5月頃に太平洋で流れ藻についたモジャコを採集し、いけすで大きく育てる海面養殖が主に西日本で行われています。
秋の深まりと共に味が良くなり、明石海峡ではハマチやブリを狙った釣り船で賑わいます。
鰆
解説

30~60cmをサゴシ、60~70cmをヤナギ、70cm~をサワラと呼ぶ出世魚です。播磨灘北部では、5~7月にかけて2隻の船を使って網で囲い込んで獲る”はなつぎ”と呼ばれる船びき網漁と、春から秋に行われる”ながせ”と呼ばれる流し刺網漁で漁獲します。
天ぷらや塩焼き、ソテーなど加熱料理に向いています。
(写真提供:姫路市)
鰶
解説

播磨地方では初夏から秋にかけて、定置網漁や底びき網漁などで漁獲されます。25cmほどになり、8cm前後をシンコ、10cm前後をコハダとも言います。
酢締めの他、刺身や塩焼き、照り焼き、天ぷらなどで食されます。身がしっかりしており、噛むごとに味わいがあります。
(写真提供:姫路市)