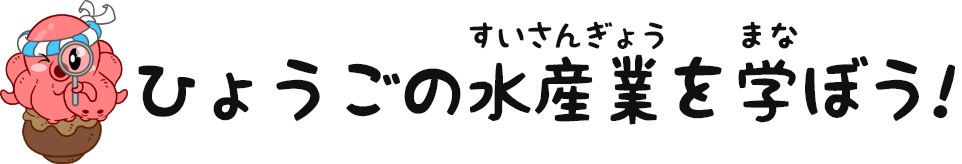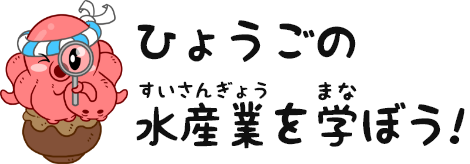古くから明石で獲られてきた水産物からランダムに10問出題します。
漢字の読み方をカタカナで回答してください。
鮻
解説

グチ、シログチ等。浮袋を伸縮させてグーッ、グーッと音を出し、この音が愚痴を言っているようなので”グチ”と呼ばれています。
播磨灘ではほぼ1年中底びき網漁で漁獲されます。身に水分が多いので南蛮漬けや塩焼き、ムニエルやつみれ等で食されます。
石鰈
解説

大きいものでは50cmほどになるカレイの一種。やや長いひし形をしています。表皮はウロコがなく、革のようにしっかりしています。
播磨灘北部では近年漁獲量が激減しており、幻のカレイになってしまいました。
繊維質のしっかりとした身質を味わえる刺身のほか、焼き物などで食されます。
(写真提供:姫路市)
白魚
解説

体長6~10cmほどの細く体幅の薄い半透明な魚です。千種川加工では、2~3月の短期間のみ産卵に来遊してくる親魚を狙った刺網漁が日暮れと共に行われ、春の風物詩となっています。
主に天ぷらや玉子とじ、吸い物にされます。
(写真提供:姫路市)
沙魚
解説

秋が旬の魚で、播磨灘北部では生息域の関係で漁業対象にはなっていませんが、秋の休日には千種川や加古川などの汽水域ではハゼ釣りで賑わいます。
くせのない白身で、天ぷらから塩焼き、煮物、汁物など様々な調理法で食されます。
(写真提供:姫路市)
赤貝
解説

殻長10cmほどになり、ふくらみが大きく、殻表面は黒褐色の短毛に覆われた放射肋(ろく)が40数本あります。
播磨灘北部では、低水温期に底びき網漁で漁獲されます。
(写真提供:姫路市)
鰤
解説

出世魚として広く知られ、関西ではモジャコ(~10cm)→ツバス(30~40cm)→ハマチ(40~50cm)→メジロ(50cm~80cm)→ブリ(80cm~)と呼び名が変わります。
5月頃に太平洋で流れ藻についたモジャコを採集し、いけすで大きく育てる海面養殖が主に西日本で行われています。
秋の深まりと共に味が良くなり、明石海峡ではハマチやブリを狙った釣り船で賑わいます。
(写真提供:姫路市)
鱠残魚
解説
シラウオのことも「鱠残魚」と書きますが、文献ではシロギスの地方名「キスゴ」のこと。播磨灘北部では主に底びき網漁で漁獲されます。
天ぷらや刺身、塩焼きをはじめ、様々な料理に利用できます。
大口鰈
解説

ヒラメのこと。昔はヒラメもカレイと呼ばれていました。
全国に分布する高級魚の一つで、播磨灘では年間を通して底びき網やたて網漁で30~80cmのヒラメが漁獲されます。
晩秋から春にかけての低水温期が旬となり、刺身や昆布締め、あら煮、天ぷらなどで食されます。
(写真提供:姫路市)