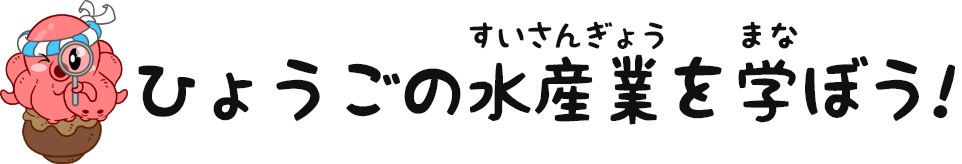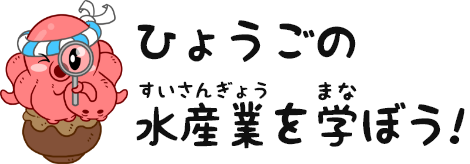古くから明石で獲られてきた水産物からランダムに10問出題します。
漢字の読み方をカタカナで回答してください。
Q1
Q2
拶双魚
答え:サッパ
解説

コノシロによく似ていますが、体長13cmほどの小型魚です。コノシロと違い背びれの後端は糸状に伸びていません。
播磨灘北部では定置網漁や巻き網漁で混獲されることもありますが、めったに市場に出ることの無い魚です。
岡山で有名なママカリは、サッパを開いて酢漬けにしたもの。
(写真提供:姫路市)
Q3
鰡
答え:ボラ
解説

大きいものでは80cm近くなり、河口周辺や沿岸域に群れで生息しています。
冬場のボラは”寒ボラ”と呼ばれ、あっさりとしながらも旨みのある美味しい魚ですが、最近では、生息場所によっては肉に臭みがあることから、市場に出ることはあまりありません。
ボラの卵巣を塩漬けにした「カラスミ」は日本三大珍味の一つです。
(写真提供:姫路市)
Q4
鱩(または 鰰)
答え:ハタハタ
解説

冷たい海水にすむ魚で、100mより深い砂や泥の海底で暮らしており、底に潜ることもあります。冬の海の荒れ、雷が鳴るときによくとれることから魚に雷と書くとの説があります。
Q5
車蝦
答え:クルマエビ
解説

体を丸めると車輪のような模様になるのでこの名があります。主に内海の砂泥底に生息していますが、全国的に環境悪化等で減少しており、天然資源を補う種苗放流が各地で行われています。
(写真提供:姫路市)
Q6
鮧鱛
答え:エソ
解説

ハダカイワシ目エソ科の海水魚の総称。アカエソ、オキエソなどがあり普通マエソを差しますが、播磨灘で見られるエソは主にトカゲエソです。
底びき網漁で混獲されますが、小骨が多く食べにくいことやまとまった量が獲れないことから市場にでることはほとんどありません。
(写真はトカゲエソ/写真提供:姫路市)