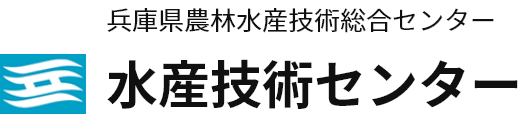試験研究課題
令和7年度 主な試験研究課題
瀬戸内海生産構造解明調査事業
瀬戸内海東部の広範な海域において、動物プランクトンを含む低次生物生産を把握するためのモニタリングを実施し、漁獲が低迷する主要な漁獲対象種の減少要因や適正な栄養塩環境を検証するために必要なデータを得る。
(担当:水産環境部)
漁場環境保全対策調査研究
本県瀬戸内海側の各漁場における環境を調査し、水質等の状況を定期的かつ継続的に把握することによって、漁場環境の保全及び海洋生物生産の変動要因の解明等に役立てる。
(担当:水産環境部)
重要赤潮被害防止対策事業(瀬戸内海)
瀬戸内海東部海域において、赤潮多発期の夏季およびノリ養殖期の冬季に関係機関で連携のとれた広域共同調査を実施し、栄養塩濃度、有害赤潮種の動態等を広域かつ経時的に把握し、瀬戸内海東部海域における有害赤潮種の出現特性等を明らかにする。また、得られた情報を迅速に漁業者等へ提供するとともに、既存データも含めたデータ解析によって赤潮発生シナリオを構築し、赤潮発生予察や漁業被害軽減に資する。
(担当:水産環境部)
瀬戸内海重要水族環境調査
本県瀬戸内海域における重要水族の資源生態と漁場環境を明らかにすることにより、漁業資源の効率的利用や沿岸漁業経営の安定化に資する。
(担当:水産環境部)
漁海況情報収集事業(瀬戸内海)
漁場環境調査や市場調査等により、漁場環境の現状や漁獲対象種の資源動向等を定期的に把握することで、漁業者をはじめとする県民への海況情報の提供や水産資源管理のために必要なデータを収集する。
(担当:水産環境部)
資源評価調査(瀬戸内海)
排他的経済水域内の漁獲許容量を把握し、我が国周辺漁業資源の適切な保存と合理的・持続的な利用を図るため、水産庁からの委託により、資源評価・動向予測・最適管理手法の検討に必要な基礎資料を整備する。
(担当:水産環境部)
海洋環境モニタリング高度化事業
低次生物生産の評価に必要な植物・動物プランクトンのデータ取得について、高度化と省力化を図るため、分子生物学的手法等の導入について、その精度や定期観測における実現可能性を検証するとともに、これまでに蓄積された50年間の海洋観測データのうち、特に2010年代以降の貧栄養化が指摘されるようになった瀬戸内海の海洋環境を評価し、今後の新たなモニタリング耐性の検討に必要な知見を収集する。
(担当:水産環境部)
増養殖推進対策調査研究
(1) 魚病対策試験調査
魚病に関する調査、技術指導を行うことでデータを集積する。
(担当:水産増殖部、内水面漁業センター)
(2) ワカメフリー配偶体の成熟促進培養技術の開発
「成熟せずに成長し続ける配偶体をいったん休眠させることで成熟させられるのではないか」という仮説のもと、長年の継代培養により成熟能力が低下した配偶体の成熟促進培養条件を明らかにする。
(担当:水産増殖部、水産環境部)
(3) ナマコ中間育成及び放流手法の開発
垂下式畜養による無給餌低コストでの幼ナマコ育成技術を改良し、育成初期の捕食生物や競合生物による減耗防止や夏季の成長停滞を軽減するための育成技術を開発する。
(担当:水産増殖部)
(4) 放流ガザミの生残率向上技術開発研究
付着生活期に適した付着基盤を検討し、基盤に適した密度、付着日数、他の生物(餌生物や食害生物)の付着状況を調べることで、ガザミの放流後、C1 から C4 までの付着生活期における生残率を向上させる。
(担当:水産増殖部)
(5) 養殖ワカメの食害実態の把握と対策技術の開発
養殖ワカメの食害実態把握と原因種を特定する。また、原因種の生態に応じた食害軽減技術を開発・実装する。
(担当:水産増殖部)
高水温耐性ニジマス系統確立と高水温耐性の評価
本県海域の水温帯でもある程度長い期間養殖ができ、十分な成長が得られるような高水温耐性ニジマスの系統を確立する。
(担当:水産増殖部)
沿岸域におけるクロダイの漁獲方法の検討及び開発
ノリ養殖場周辺に生息するクロダイの効率的な漁獲方法を検討・開発し、養殖ノリの食害軽減を図る。
(担当:水産増殖部)
アユ資源維持増強対策調査研究
(1)アユ資源維持増大対策調査研究
(1)アユ冷水病の保菌検査を実施することによって冷水病菌の河川への拡散を防止するとともに、新たな感染症の保菌検査も実施する。
(2)遺伝子解析結果により、アユ資源増殖手法を明らかにし、付加価値向上についても検討する。
(担当:内水面漁業センター)
(2) アユ流下仔魚の海洋生活期調査研究
海洋生活期の生息地調査、遡上量調査及び親魚放流の効果把握を行う。
(担当:内水面漁業センター)